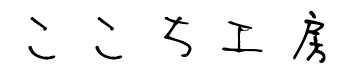550X400
こんにちは。36色 色鉛筆で描く『ここち工房』Hiroko. です。色鉛筆で心地いい暮らしを広めたくて、ブログを始めました。
秋はリンゴの美味しい季節。
青リンゴをいただいたので形のきれいなものを並べて描いてみました。
『王林』は青リンゴ界の王様だそうです。
見た目は、青みがかった皮に果点と呼ばれる点がたくさんあって、甘くなさそうなのですが、味はさっぱりとしていてクセもなく、とても甘くて美味しかったです。甘い香りが美味しさをひき立たせてくれました。
私の描いた作品のポイントや考え方を、手順に沿って簡単にまとめています。この絵が少しでも気に入ってくれたら、参考にして下さい。
Table of Contents
青リンゴのポイント解説と手順
色鉛筆について・塗り方説明
色鉛筆について 初心者の人が趣味として手軽に始めるには、最初に高い色鉛筆や画材をそろえることではなく、絵を描く楽しさを知ること。 その後でいろんな画材を試し、そろえていくのがいいと思います。最初からたくさんの色鉛筆をそろえるのではなく36色から始めるのがおすすめです。 どの色鉛筆がいいのか私なりにいろいろと試した結果、三菱色鉛筆No..880〈36色セット〉となりました。ここは好みでいいですよ。 絵を描くのに36色あれば十分表現できます。私の全ての作品は、この36色で描いています。
塗り方の説明はここをチェック
使用道具はここをチェック
絵の構図の考え方
同じ形のもの(丸いもの)は積み重ねたり、均一に並べて描くことが多いです。
シンプルな形をキレイに見せたいからです。
数は偶数より奇数にすることが多い。
日本では陰陽道の考えが広く伝承され、奇数が「陽の数」として縁起が良かったりバランスが良いとされているそうです。絵には関係ないと思いますが…。
青リンゴは5つともほぼ色が一緒だったのですぐに出来上がりました。
でも途中で構図に悩みました。
最初に決めた構図には下に引くクロスはありませんでしたが
リンゴを塗っている途中で木の色と青リンゴの色の間にアクセントがほしくなり、クロスを追加しました。
木の素材だけではリンゴの色が引き立たないと思ったからです。
構図の変更はあまりしない方ですが
途中で思い立って追加しました。
木目を縦にするか横にするか?
全体の雰囲気が変わるのでとても重要です。
今回は、クロスとリンゴを横にして、木目を縦に。絵の奥行き感を強調することにしました。
クロスの色について。
途中で追加したので何色のクロスで青リンゴを引き立たせるか?
持っているクロスの中で考えた結果、質感を強調する目の粗い生地感のある白いキッチンクロスにしました。
生地の質感や色で全体の雰囲気が変わってしまいます。いい生地に出会えた時は迷わず購入ですね☺️
青リンゴを描くときのポイント4つ
ポイント ⑴青リンゴの色と影 ⑵キッチンクロスの素材(質感の出し方) ⑶木目の色(質感の出し方) ⑷光と影
⑴青リンゴの色と影
青リンゴの色は短調になりがちなので下地に”あかむらさき”を薄く塗ります。
リンゴは青みどりですが、微妙に赤が入っているんです。
光の当たっているところは白ヌキにして影はしっかりと。
影には”くろ”は塗らずに”ぐんじょいろ”をたくさん塗りました。
ヘタの部分は陰影をしっかりつけて立体的に描きます。
リンゴを並べる順番はヘタの向きで決める。
真ん中は上向き!
これはすぐに決めたのですが、並べるときにヘタの向きで悩み、
5つのリンゴのバランスと絵全体の雰囲気をみて決めました。
⑵キッチンクロスの素材(質感の出し方)
クロスは、あまりシワを出さずにすっきりと!
シワがないと影もすっきりするのでその方がリンゴの丸さを表現できます。
つるんとした生地ではなく、オーガニック生地の素材感をラインを出して強調しました。
“はいいろ””たまごいろ””ちゃいろ””うすむらさき”で生地の粗さを表現。
前の方の厚み感も出したかったので、少し濃い目に仕上げました。
リンゴ1個1個の存在感を出すために、クロス下のリンゴの影は生地の粗さを出しながらラインを少し濃い目に入れました。
⑶木目の色(質感の出し方)
あまりゴツゴツしないように、つるんとしたイメージで描きました。
実際は節がたくさんありましたが…そこは省略し、リンゴの青みどりとクロスの白を引き立たせるために木の色を青みどりっぽくしてトーンをおさえました。
その方が全体の統一感が出ます。
木は茶色のイメージがありますよね!最初に茶色を塗ってしまいがちですが、今回はすっきりしたイメージにするために青みどりっぽく。
木を青みどりっぽくする為には、最初と最後に”うすむらさき”と”ぐんじょいろ”を塗ります。
木は茶色!葉っぱは緑!など…イメージにとらわれないで、絵の中の色に合わせて変えてみるのもいいでしょう。
⑷光と影
それぞれの素材に合わせて光の入れ方を変える。
反射するものとしないもの。それだけでも表現のしかたが変わってくる。
光はあとから消しゴムで消すこともできますが、一度塗ると真っ白にはできないので、最初から白ヌキしてイメージをつかんでおく必要があります。
- リンゴの皮を表現するために白ヌキ多め。
- クロスは反射しないので光は素材の色だけで表現。
- 木はつるつるしているが、反射少なめで奥行き感を表現するために前と奥の色の差に注意しながら濃淡をつける。
- クロスの影は、木の影をしっかり濃い目にして、柔らかさと厚み感を出す。
まとめ

まとめ ⑴青リンゴの色と影 ※下地に注意 ⑵キッチンクロスの素材(質感の出し方)※素材感をラインを出して強調 ⑶木目の色(質感の出し方)※イメージにとらわれない ⑷光と影 ※イメージをつかんでおく必要がある
全体的にすっきりとしたイメージ通りの青リンゴの絵になりました。
リンゴはたくさん描いてきましたが、とても形の描きやすい題材だと思います。
同じ素材を描くときの構図は難しいですが、最初は1個から…。
徐々に数を増やして挑戦してみてくださいね。
どの色鉛筆がいいのか私なりにいろいろと試した結果、三菱色鉛筆No..880〈36色セット〉となりました。ここは好みでいいですよ。
絵を描くのに36色あれば十分表現できます。私の全ての作品は、この36色で描いています。
最後に
ブログ初心者で言葉のチョイスが難しく、うまく伝わるか不安ですが…。
この絵を見た人が、描いた時の私の思いと同じことを感じてくれたらうれしいです。人を惹きつけるには、一瞬の印象だと思います。そんな作品を描きたい。
その思いが伝わったときの感覚はたまりません!
絵を描くのは、自分だけの趣味や楽しみもあるけど、知らない人に絵を見てもらい、絵の話しをしたりする楽しみもある。
物で満足していた時代から、これからは、想像もつかない出会いや価値に意味を見いだすことが大切なのではないでしょうか。
私自身、絵を通してたくさんの人に知り合えました。
36本の色鉛筆でステキな経験と出会いができると思います。 色鉛筆で心地良い暮らしを始めましょう。
最後までありがとうございました。